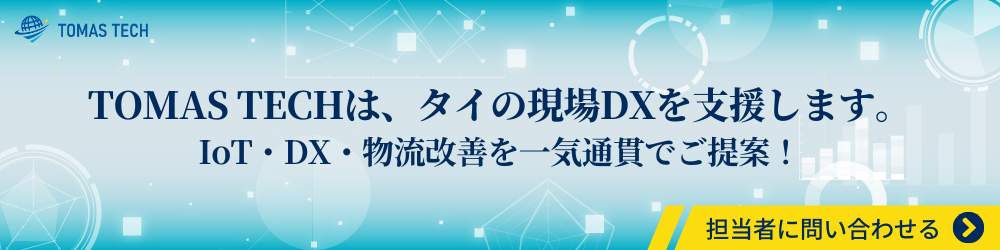タイに製造拠点を持つ日系企業のマネージャーやIT担当者の中には、本社から「DX(デジタルトランスフォーメーション)を推進しましょう」と指示されても、何から始めれば良いか悩んでいる方も多いのではないでしょうか。
DXとは、デジタル技術を活用して業務プロセスやビジネスモデルを変革する取り組みのことです。
ただしDX=工場の全自動化ではなく、小さな改善を積み重ねて現場に根付かせることが成功のカギです。
この記事では、タイの製造業におけるDX推進の背景から、現場の課題、段階的に進める具体的ステップ、導入事例、そしてよくある質問までやさしく解説します。DXに踏み出せずにいるご担当者の不安に寄り添い、解決策をご紹介します。
タイ製造業でDXが求められている背景

まず、なぜ今タイの製造業でDXが求められているのでしょうか。その背景には経営環境の変化と労働環境の変化があります。 タイはASEAN有数の工業国で、食品・石油化学・電子部品など多様な製造業が集積し、日系企業も多数進出しています。
近年は市場ニーズの変化や中国系企業の台頭など競争が激化しており、従来のやり方を見直す必要性が高まっています。またタイ政府は2015年に「タイランド4.0」と呼ばれる国家ビジョンを掲げ、次世代産業の育成や製造業の高度化を推進しています。
その流れを受け、各製造企業にもデジタル技術を活用した省人化・効率化や品質向上、すなわちDXへの取り組みが求められているのです。 さらにタイでは少子化により生産年齢人口の減少が見込まれており、将来的な人手不足への対策も急務です。
日本の本社から海外工場の生産性向上や業務標準化を求める声も強まっており、DXは不可欠です。このように市場・政策面と労働力面の双方から、タイの製造現場にDX推進の圧力が高まっている状況です。
参照元:デジタル化や脱炭素に、日系企業は(タイ) | 地域・分析レポート – 海外ビジネス情報 – ジェトロ
タイ製造業によくある現場の課題とDXの必要性

次に、タイの製造現場でよく見られる課題と、それに対してなぜDXが必要とされるのかを見ていきましょう。皆さんの職場でも思い当たる点がないか、照らし合わせながらお読みください。
紙・口頭・ホワイトボードでの管理
生産状況をリアルタイムで把握できず、問題の発見・対応が遅れてしまう──これは多くの工場で見られる課題です。紙のチェックシートや手作業の集計では情報にタイムラグが生じ、ミスも発生しがちです。
現場データの見える化ができていなければ、ムダやボトルネックを迅速に発見して改善することができません。まずDXによって現場のデータを収集・可視化する土台を作らなければ、効率化のスタートラインに立てません。
属人的な管理に依存している
タイでは人材のジョブホッピング(転職による流出)が多く、従業員や駐在員が交代する度にノウハウが失われてしまうという構造的課題があります。
属人的なやり方に頼っていると品質や生産性の維持が難しくなりますが、DXによって作業手順やノウハウをデジタルで標準化し共有すれば、担当者が替わっても現場力を落とさずに済みます。人に依存しない仕組みを作るためにも、DXは必要不可欠なのです。
参照元:DXを通じた業務標準化に貢献(タイ) | 地域・分析レポート – 海外ビジネス情報 – ジェトロ
現場の情報が集約されず、改善が進まない
工場内外の情報連携がスムーズでないことも大きな課題です。生産が完了しても在庫データへの反映や本社への報告に時間がかかる、機械の故障情報が関係部署にすぐ共有されない──こうしたケースが見られます。
これは、生産管理・在庫管理・保守管理などのシステムが分断され、データ連携できていないためです。DXにより工場内の工程データと在庫・販売システムをつなげれば、伝達遅れによるムダを省き、在庫切れや過剰生産の防止にもつながります。
現場でのお悩みがある方は、ぜひDXによる解決に一歩踏み出してみましょう。TOMASTECH担当者にご相談ください。
タイでのDXを成功させる3ステップ

では、具体的に現場でDXを進めるにはどのような手順を踏めば良いのでしょうか。「何から始めればいいのか分からない」という方向けに、タイの製造現場で実践しやすい3つのステップをご紹介します。
いきなり高度なことを目指す必要はありません。順を追って段階的に進めていきましょう。
ステップ1:現場の“非効率”を洗い出す
最初のステップは、現場の見える化を開始することです。まず工場内で改善したい課題を一つ選び、それに関するデータを小規模に収集する仕組みを導入してみましょう。
例えば、一部の設備にIoTセンサーを取り付けて稼働時間を測定する、紙の日報をタブレット入力に変える、といった取り組みです。工場全体を一度に変える必要はありません。限定した範囲からデジタル化を試すことで、勘や経験に頼っていた問題の原因を客観的に把握できるようになります。
ステップ2:スモールスタートでデジタル化
次のステップは、データから判明した問題に対して改善策を講じることです。ステップ1で集めたデータを分析し、優先度の高い課題を一つ選んでデジタル技術も活用しながら現場で解決策を試してみます。
例えば、機械の故障が頻発しているなら予防保全を導入する、進捗状況が見えないなら作業管理システムを試す、といった具合です。 ここで小さな成功体験を作ることがポイントです。
一つのラインでIoT監視を導入して待ち時間を短縮できたら、その成功事例を現場全体で共有し、「便利だ」「他でも試してみよう」という雰囲気を醸成します。DXの効果を現場の人が実感できれば、抵抗感も薄れ、協力も得やすくなります。
ステップ3:システム間連携と可視化を強化
最後のステップは、得られた効果を横展開して全体最適化を図ることです。ステップ2で上手くいった方法があれば、それを他の設備やラインにも広げていきましょう。また、個別に導入したシステム同士を連携し、工場全体でデータを一元管理できるようにします。
例えば、生産データと在庫システムを連動させて在庫情報を自動更新する、本社の基幹システムと接続してグローバルに標準化するといった発展も可能です。点在していた改善を線でつなぎ、工場内外の情報がシームレスにつながる体制を整えることで、DXの恩恵を最大限に引き出せます。
実際に成果が出たタイ製造業DX導入事例

「段階的に進めると言っても、本当に成果が出るのだろうか…」と不安に思う方もいるかもしれません。そこで、タイの製造業でDX導入によって実際に大きな成果を上げた事例を一つご紹介します。
ある日系メーカーのタイ工場でIoTを導入した結果、ダウンタイムが80%削減、生産量が約2倍に向上した事例があります。
このように、DXに取り組むことで定量的にも大きな効果が得られることが実証されています。もちろん全てのケースで同じ成果が出るとは限りませんが、小さな改善でも積み重ねていけば数年後には驚くほどの生産性向上につながる可能性があります。ぜひ貴社でも、できるところからDXを始めてみてください。
タイ製造業DX化に関するよくある質問

ここからは、タイ製造業DX化に関するよくある質問に回答していきます。
いいえ、DX=フルオートメーションではありません。ロボットやAIの活用もDXの一部ですが、それだけがゴールではないのです。DXの本質はデジタル技術で業務の進め方をより良く変えることで、人と技術を組み合わせて価値を生み出す取り組みです。自動化は手段の一つに過ぎず、目的はあくまで現場の改善にあります。
必ずしも巨額の投資が必要というわけではありません。小さく始めれば、既存設備に安価なIoTセンサーを後付けして稼働データを集める程度の投資で済みます。またクラウドサービスを活用すれば自社サーバーは不要で、初期費用を抑えて必要なシステムを利用できます。
重要なのは費用対効果を見極めながら段階的に投資することです。小さな成功で得た成果をもとに次の予算を確保していけば、無駄なくDXを進められるでしょう。
TOMAS TECHが提供するタイ製造業DX支援

「自社だけでDXを進めるのは心細い。頼れるパートナーにサポートしてほしい」──そのようにお感じでしたら、タイ進出企業向けにDX支援サービスを提供しているTOMAS TECHの活用をご検討ください。
TOMAS TECHはタイの製造業に特化したDX支援をワンストップで提供しており、「何から始めればいいか」という段階から現場に寄り添って伴走します。それぞれの工場に合った段階的プランを提案し、小さな成功体験を積み重ねながら大きな成果へ導くことを目指しています。 主なサービス内容をご紹介します。
- IoT導入支援:工場設備にセンサーを取り付けて稼働データを収集し、見える化や異常検知を実現します。
- 工程管理のデジタル化:生産ラインの進捗や作業手順を管理するシステムを構築します。リアルタイムで現場の状況を把握できます。
- 在庫・基幹システム連携:工場の生産データと在庫管理システムやERP(基幹システム)を連携させます。生産と在庫の情報を同期することで、在庫切れや過剰在庫を防げます。
このほか、現場スタッフ向けのIT研修や日本語・タイ語でのサポートなど、「現場に根付くまで」きめ細かな支援を行っています。
DXもTOMAS TECHと二人三脚で進めれば安心です。まずはお気軽にお問い合わせください。
まとめ:タイ製造業のDXは“段階的改善”が成功の鍵
タイの製造業におけるDX推進について、背景から具体策まで見てきました。重要なのは、DXを特別なものと構えずに現場の小さな改善を積み重ねていくことです。
すべてを一度に変える必要はありません。焦らず着実に進めることが成功への近道です。今日からできることに取り組んでみてください。
小さな一歩が数年後の大きな飛躍につながると信じて、ぜひDXにチャレンジしてみましょう。