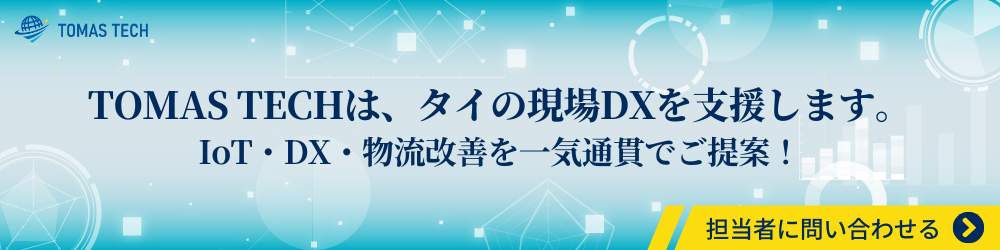タイの自動車産業は「アジアのデトロイト」と呼ばれ、日本メーカーを中心に大規模な生産拠点を形成してきました。しかし近年は内需低迷や家計債務の増加、さらに電動化の波による部品サプライチェーンの再編といった課題に直面しています。
政府は「30/30政策」やEV3.5政策を打ち出し、2030年までに新車生産の30%をゼロエミッション車にする目標を掲げています。
本記事ではタイの自動車産業の現状と課題を整理し、在庫・品質・人材不足を解決するDXの導入ステップや、TOMAS TECHが支援するトレーサビリティ事例を紹介します。
タイの自動車産業の現在地と市場動向

ここでは、タイ自動車産業の基盤となる生産・輸出の動きや国内需要の現状、そして日本メーカーと中国メーカーの競争状況について解説します。
生産台数と輸出台数の推移
タイの自動車産業は「アジアのデトロイト」と呼ばれ、ASEAN随一の生産拠点として発展してきました。2024年の生産台数は約146万台に達し、そのうち半数以上が輸出向けとなっています。
特にピックアップトラックは主要輸出品で、中東やオーストラリアなど世界各地で高いシェアを誇ります。一方で乗用車の国内需要は伸び悩み、生産全体を下支えしているのは輸出市場というのが実情です。
内需低迷と家計債務の影響
国内販売が停滞する大きな要因は、タイ特有の家計債務問題にあります。新車購入のためのローン審査が厳格化され、購買層が広がりにくい状況が続いています【JETRO「自動車の内需不振を輸出が補えず」】。
若年層ではカーシェアリングやライドシェアサービスを選ぶ傾向も強まり、かつてのような旺盛な需要は見られません。こうした構造変化により、メーカーは国内市場だけに依存する戦略から輸出とEV投入を組み合わせた多角的な施策へと舵を切っています。
参照元:自動車の内需不振を輸出が補えず(タイ) | 地域・分析レポート – 海外ビジネス情報 – ジェトロ
日本・中国メーカーの競争状況
これまでタイ市場を支配してきたのは日本メーカーでした。トヨタ、ホンダ、日産、三菱などのシェアは依然6割以上を占めますが、その地位は安泰ではありません。政府の補助金制度を追い風に、中国メーカーが急速に勢力を拡大しているからです。
BYDやMG(SAIC傘下)といったブランドは、EV分野で存在感を高め、販売台数を伸ばしています。日本勢も現地でのEV生産やバッテリー投資に乗り出していますが、電動化対応のスピードは今後の競争力を左右する決定的要因になるでしょう。
参照元:地域・分析レポート | 海外ビジネス情報 – ジェトロ
タイの自動車産業に影響するEV化と規制動向

続いて、タイ政府が推進する「30/30政策」やEV3.0/3.5政策の概要を整理し、電動化が部品サプライチェーンやバッテリー産業に及ぼす影響を見ていきます。
30/30政策とEV3.0/3.5政策の内容
タイ政府は「30/30政策」を掲げ、2030年までに新車生産の30%をゼロエミッション車にする方針を示しました。これを実現するため、EV購入補助や法人向け税制優遇を含む「EV3.0政策」が導入され、さらに現地生産義務を強化した「EV3.5政策」が追加されています。
政策の狙いは単なるEV普及ではなく、部品サプライチェーンを国内に取り込み、タイをアジアのEV生産拠点として確立することにあります。
EV普及に伴う部品サプライチェーンの再編
電動化の加速は部品産業に深刻な影響を及ぼしています。エンジン部品の需要が縮小する一方、バッテリーやインバーター、充電設備といった新しい領域の需要が急拡大しています。
これまで内燃機関で優位にあった中小サプライヤーは、技術転換や新規投資を迫られています。外資との合弁や技術提携を通じた生き残り戦略も進み、産業構造全体が大きな再編期に入ったといえるでしょう。
バッテリー製造・現地化要件
EV政策において特に注目されるのが「現地化要件」です。BOIの優遇策では、一定割合のバッテリーをタイ国内で製造することが条件とされています。
このため中国や韓国の大手バッテリーメーカーが次々と投資を決定し、現地生産体制を整えています。国内サプライチェーンの整備が進むことで雇用や技術移転の効果も期待され、タイの自動車産業に新たな成長エンジンが加わろうとしています。
タイの自動車産業が抱える現場課題とボトルネック

次に、タイ自動車産業の現場で直面している在庫管理の難しさ、品質リスク、そして慢性的な人材不足と教育コストの課題について取り上げます。
在庫過多・欠品リスク
需要変動や物流遅延により、在庫の過不足が頻発しています。部品が余れば保管コストを圧迫し、不足すればラインが止まる。タイの自動車産業にとって二重のリスクは常に現場を悩ませる要因です。
特に輸出依存度が高い産業構造では、海外物流の乱れがダイレクトに影響します。適正在庫を維持する仕組みの構築が急務といえるでしょう。
参照元:自動車の内需不振を輸出が補えず(タイ) | 地域・分析レポート – 海外ビジネス情報 – ジェトロ
品質トラブルとリコール対応の負担
品質トラブルが発生すると、一度に数千台規模のリコールにつながることがあります。輸出先での不具合はブランド信頼を一気に損なうリスクを抱えています。
発生源をすぐに特定できる体制を持つかどうかで、その後の対応スピードは大きく変わります。ロット単位の実績管理やトレーサビリティの強化は、今や競争力を左右する要件となっています。
慢性的な人手不足と教育コスト
労働人口の減少と人材流動化により、現場は人手不足に直面しています。新規採用を行っても教育に時間とコストがかかり、多言語環境での指導が不可欠です。
現場では「人材が定着しない」「教育コストが重い」という声が上がっており、標準化された仕組みの導入が求められています。
参照元:人材不足の現状と対応、今後の最低賃金の動向にも注目(タイ) | アジア大洋州地域の人材確保・賃金高騰の現状と対応 – 特集 – 地域・分析レポート – 海外ビジネス情報 – ジェトロ
タイの自動車産業を変革するDX導入のステップ

ここからは、課題解決に向けたDX導入の具体的なアプローチを紹介します。小規模導入から全体展開、統合設計、多言語対応まで順を追って見ていきましょう。
部分導入から全体展開(事例紹介)
DXを進める際にいきなり全社展開を行うのは現実的ではありません。多くの製造業では、まず1ラインや1工程からスタートし、小規模な成功体験を積み上げることが有効です。たとえば、特定工程にMES(製造実行システム)を導入し、生産実績をロット単位で収集するなど。
これにより品質トラブルが発生した際、影響範囲を正確に絞り込めるようになりました。その後、仕掛品や在庫管理にも範囲を広げ、工場全体へ展開することで大きな成果につながっています。段階的な導入は教育負担を抑え、投資効果を見極めやすいという利点もあります。
在庫・生産・トレーサビリティの統合設計
在庫管理と生産実績、さらにトレーサビリティを別々に扱うと、現場での情報伝達が遅れがちです。システムを統合すれば、原材料の投入から完成品の出荷までを一気通貫で追跡できます。
特に輸出比率の高いタイの自動車産業では、輸出先国の規制対応や顧客監査において「どのロットで生産されたか」を即座に提示できる体制が不可欠です。情報が統合されていれば、現場の判断スピードも上がり、在庫過多や欠品リスクの削減にも直結します。
多言語UIによる教育負担の軽減
現場運用で見落とせないのが教育コストです。タイ工場では日本人駐在員、タイ人作業者、さらに外資系のスタッフが混在して働くケースが珍しくありません。紙マニュアルや属人的な指導では、定着に時間がかかります。
そこで効果を発揮するのが、多言語対応のユーザーインターフェースです。日本語・英語・タイ語の切り替えを標準機能とすることで、教育期間を短縮し、現場への定着率を高められます。結果として、人材不足が慢性化するタイの自動車産業において、限られたリソースを最大限活用する仕組みとなるのです。
タイの自動車産業の成果を高める運用と効果測定

最後に、DXを定着させるための運用と効果測定のポイントを解説します。リアルタイム可視化、リコール対応力、KPI管理を中心に整理します。
ダッシュボードによるリアルタイム可視化
現場のデータを活用できなければDXは形骸化します。TOMAS TECHのシステムでは、稼働状況・品質・仕掛品数をリアルタイムでダッシュボードに表示できます。経営層と現場が同じデータを即座に共有できることで、異常が発生した際の対応スピードは格段に向上します。
情報がタイムリーに見える化されることは、改善サイクルを回すうえで欠かせない条件です。
ロット単位の実績収集で強化されるリコール対応力
タイの自動車産業においては、リコール対応力の強化が企業の信頼を守るカギです。TOMAS TECHの導入事例では、製造実績をロット単位で収集した結果、問題が発生した際に対象範囲を迅速に特定できるようになりまし。
その効果は、リコールコストの削減だけでなく、顧客や監督当局への説明責任を果たす上でも大きな意味を持ちます。信頼性の高い供給体制は、輸出市場での競争力を高める要因となります。
KPI管理と改善サイクルの定着
DX導入は一度で終わりではありません。KPIを明確に設定し、定期的に効果を測定して改善につなげることが重要です。たとえば「不良率の削減」「在庫回転率の向上」「納期遵守率の改善」といった指標を見える化することで、現場と経営層が同じゴールを共有できます。
改善サイクルが定着すれば、DXは単なるシステム導入にとどまらず、組織文化の変革へと発展していくのです。
タイの自動車産業に関するよくある質問

タイ自動車産業については「なぜ成長してきたのか」「日本メーカーのシェアはどの程度か」「撤退のニュースは何を意味するのか」といった疑問が多く寄せられます。ここでは特によくある質問を整理し、分かりやすく解説します。
タイの自動車産業はなぜ「東南アジアのデトロイト」と呼ばれるのですか?
タイはASEAN最大の自動車生産国であり、世界市場に向けた輸出拠点を築いてきました。特にピックアップトラックの生産では国際的に高いシェアを持ちます。ただし近年はEV化や中国メーカーの台頭により、構造転換が求められています。
日本メーカーはタイでどの程度のシェアを占めていますか?
トヨタ、ホンダ、三菱、日産といった日本メーカーは依然として全体の6割以上のシェアを持っています。
日本ブランドが販売上位を維持してきましたが、近年は中国勢のEV攻勢でシェアが低下。直近データでも日本勢の合算シェアは前年から低下しています。
タイで自動車メーカーの撤退が報じられるのはなぜですか?
ホンダやスズキが一部工場を再編したことが話題になりましたが、これは需要低迷や電動化投資への対応に伴う戦略的判断です。市場そのものが縮小しているのではなく、再投資や新規参入も進んでいます。
タイの自動車産業の販売台数や推移はどうですか?
国内販売は家計債務やローン規制の影響で伸び悩んでいます。一方、輸出は堅調で、生産全体を支える柱になっています。今後は政府のEV普及政策により市場構造が変化していく見通しです。
DXやトレーサビリティ導入の具体的な事例はありますか?
TOMAS TECHが支援した事例では、MES導入により在庫・生産・トレーサビリティを統合。ロット単位の実績収集を可能にし、リコール対応力を強化しました。
タイの自動車産業のまとめ

タイの自動車産業は輸出を中心に成長を続ける一方で、内需低迷や人材不足、品質リスクなど複雑な課題を抱えています。さらにEV化政策や現地化要件により、サプライチェーンの再編も避けられません。こうした変化に対応するためには、在庫・生産・トレーサビリティを統合したDX導入が不可欠です。
タイの自動車産業は、EV化・規制対応・人材不足など複数の課題を同時に抱えています。現場の改善やDX導入を検討していても、「どこから手を付けるべきか分からない」と感じる方も多いのではないでしょうか。
TOMAS TECHでは、在庫・生産・トレーサビリティを統合するMESソリューションを通じて、現場の課題を一歩ずつ解決するお手伝いをしています。小規模導入から拠点全体への展開まで、御社の状況に合わせた最適なプランをご提案可能です。
まずはお気軽にご相談ください。担当コンサルタントが現状を丁寧にヒアリングし、改善の方向性を一緒に描いてまいります。