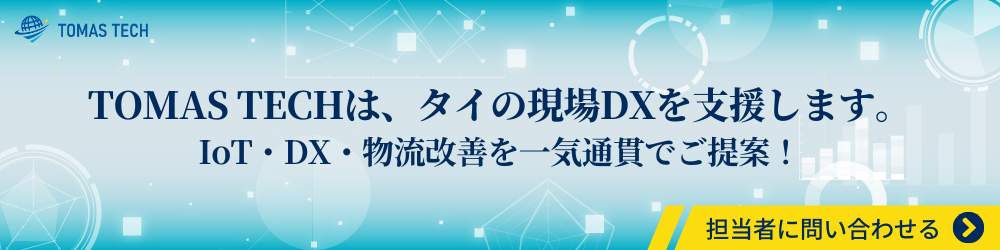タイ政府はEV(電気自動車)産業を国家戦略の中心に据え、脱炭素と産業競争力の両立を目指しています。EV補助金は、完成車だけでなくバッテリーやインフラ、リサイクルまでを含むエコシステム全体を対象に設計されており、BOI制度との併用で法人税や関税の優遇措置も受けられます。
RCEPやFTAなどの輸出優遇と組み合わせることで、タイ国内だけでなくグローバル市場への展開も強力に後押しされます。
本記事では、タイEV補助金の政策背景、支援対象、関連制度との連携、申請手順、注意点などを体系的に整理し、製造業を中心とした日系企業が実際に活用するための具体的な視点とステップを解説します。
タイEV補助金の背景と政策の全体像

タイ政府は、脱炭素社会の実現と産業競争力の強化を両立させるため、EV(電気自動車)産業を国家戦略の中核に据えています。タイEV補助金は、バッテリー製造からリサイクルまでを見据えた産業エコシステム構築を支援する仕組みです。本節では、その背景と全体像を3つの視点で整理します。
国家戦略にEV産業を組み込む背景
タイは国内GDPの約10%を占める自動車産業を、環境・経済両面の成長ドライバーと位置づけています。EV関連技術の導入を通じて温室効果ガス削減を評価対象とする新たな優遇措置を導入し、製造ラインへの設備投資に対する法人税・輸入関税の免除枠を拡大しました。これにより、企業はタイEV補助金を活用して最新鋭のバッテリー製造技術や生産設備を導入しやすくなっています。
完成車からエコシステム構築へシフトする流れ
従来の補助策は完成車メーカー向けにとどまっていましたが、現在は部品サプライヤーや充電インフラ、バッテリーリサイクルまでを含む広域支援体制へと進化しています。具体的には、リチウムイオン電池の生産ライン設置時に輸入関税と法人税を免除するとともに、廃棄バッテリーのリユース・リサイクル設備にも補助が適用されます。このように、サプライチェーン全体を視野に入れた支援策が、タイEV補助金の大きな特徴です。
産業競争力や輸出政策との関連
タイはRCEPをはじめ多数のFTA網を活用しており、EV部品や完成車の輸出時にも優遇措置が適用されます。BOI制度による輸出向け原材料の輸入関税免除は、グローバル市場での価格競争力を直接高める施策です。加えて、政府は輸出促進と並行して国内生産拠点の高度化を支援し、長期的な産業競争力強化を図っています。これらの政策はすべて、タイEV補助金を含む一連の支援策と密接に連携しています。
タイEV補助金で活用できる制度の種類

EV産業の成長に向け、タイではBOI制度をはじめ複数の支援施策が用意されています。ここでは、タイEV補助金と併せて活用できる代表的な制度を3つの視点でご紹介します。
BOI制度で対象となるEV関連事業
BOI(タイ投資委員会)が定める奨励産業には、EVの製造・組立を含む「電気・電子機器」分野が含まれます。
新規EVバッテリー工場やEVモーター組立ラインは、法人所得税免除や機械輸入税の免除対象になります。
輸出用部品の原材料輸入税も減免されるため、グローバル市場展開を視野に入れたタイEV補助金活用が可能です。
補助金・BOIで得られる恩典
BOI認定を受けることで、以下の恩典を受けられます。
- 法人所得税の免除・減税:投資額の50~100%を上限に、最大10年の免税期間
- 機械・設備の輸入関税免除:EV製造に必要なロボットや自動化機器、バッテリー製造装置が対象
- 土地所有権の取得緩和:BOI奨励取得により、外資100%で土地取得が可能になる場合があります
これらの恩典を組み合わせることで、タイEV補助金とBOI制度の相乗効果を最大化できます。
他の政府支援制度との併用
EV製造ライン刷新やDX推進には、国の補助金を併用することでさらに支援を拡充できます。主な制度例は以下のとおりです。
| 補助金名 | 対象内容 | 補助上限 | 備考 |
| 中小企業省力化投資補助金 | 自動化ロボット、物流機器 | 1億円 | 省力化カタログ型/一般型 ※要件確認 |
| IT導入補助金 | 生産管理システム、AI検査ツール等 | 450万円 | DX推進向けITツール導入を支援 |
| ものづくり補助金 | MES、エネルギー管理システムなど | 4,000万円 | 高付加価値化枠・グローバル枠あり |
これらをタイEV補助金やBOI制度と合わせて申請することで、EV製造ラインの自動化から生産管理の高度化まで、幅広い支援を受けられます。
タイEV補助金の対象となるシステム導入内容

タイEV補助金を活用するには、「補助金の要件を満たす設備・技術」と「事業計画の整合性」をクリアする必要があります。以下では、3つのポイントで解説します。
対象となる設備・技術の要件を確認する
対象となる設備・技術は、公募要領に定められた「性能基準」を満たしているかどうかが最重要です。まず、補助金要件書に記載される以下の数値目標を確認しましょう。
- 省エネ率
- 生産性向上率
- 品質管理スペック
次に、導入予定機器の仕様書と1対1で照合する「要件マトリクス」を作成します。たとえば、自動化ロボットなら「従来比○%以上の稼働率向上」、精密加工機は「○ミクロン以下の公差維持」、EMSは「電力消費量可視化ログ機能」を満たすかをチェック。
要件を明示した発注仕様書(RFP)を整備し、公募事務局への事前相談で適合性を確認すれば、交付決定後の手戻りを防げます。
MES・AI検査・エネルギー管理を導入する
製造現場の“見える化”と品質向上には、MES(製造実行システム)、AI検査装置、エネルギー管理システムの導入が効果的です。
- MES:生産進捗や設備稼働状況をリアルタイムで把握し、トレーサビリティを確保
- AI検査装置:外観や寸法、微細欠陥を自動検出し、不良品流出を防ぐ
- エネルギー管理システム:消費電力をモニタリングし、省エネ運転を自動制御。
これらを組み合わせることで、品質とコストの両面で競争力を高められます。
技術仕様と補助要件の整合性を確保する
技術仕様と補助要件の整合性を確保しましょう。導入予定の機器・システムが補助金の「性能基準」とズレると、交付決定後に追加説明や返還リスクが発生します。
まず、公募要件書にある「稼働率」「省エネ率」「検査精度」などを抽出し、導入機器のカタログスペックと照合するマトリクスを作成します。次に、その要件を盛り込んだ発注仕様書(RFP)をパートナーへ提示し、見積段階で適合性を確認。
最後に、申請前の事前相談で公募事務局へ技術概要を提出し、適合可否のフィードバックを得ることで、仕様ズレを未然に防げます。これにより、要件ギャップによる手戻りやコスト増を抑制できます。
EVエコシステム構築に向けた重点支援領域
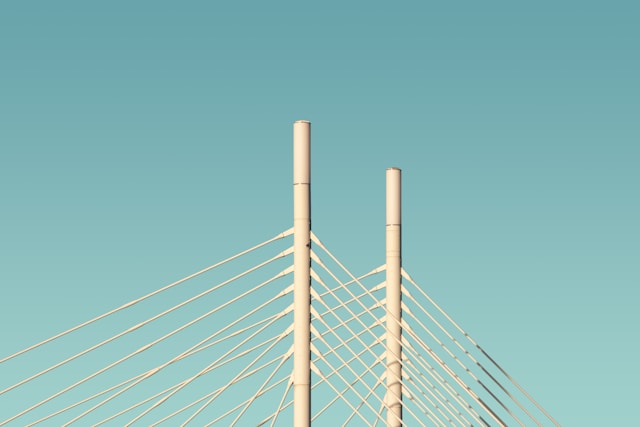
EV産業の持続的発展には、単なる車両製造支援を超えたサプライチェーン全体の整備が不可欠です。ここでは、タイEV補助金を活用しながら特に注力すべき3つの支援領域を解説します。
バッテリーリサイクルと履歴管理を整備する
使用済みバッテリーは環境負荷低減の観点から回収・リサイクルが必須です。補助金制度では、リサイクルプラントの設置や廃棄バッテリーの成分分析設備導入が対象になります。加えて、各セルの製造・使用履歴をデータベース化し、廃棄プロセスの透明性を高めるシステム構築も補助対象です。これにより、廃棄物が適切に再利用され、企業のESG評価も向上します。
使用済み資源の追跡・シリアル管理を導入する
バッテリーセルや重要部品にはシリアル番号を付与し、製造から廃棄までのライフサイクルを追跡できる仕組みが求められます。IoTセンサーやバーコード/RFIDシステムを活用し、工場内外での位置情報や稼働状況をリアルタイムに記録。補助金では、これらのトレーサビリティシステム導入費用が認められるため、品質保証と製品回収効率を同時に向上できます。
人材育成と現場運用体制を強化する
高度化したEV生産ラインには専門知識を持つオペレーターが不可欠です。補助金制度では、研修プログラム開発や外部講師招聘によるトレーニング費用も対象になります。さらに、TOMASTECHの支援では、現地スタッフ向けマニュアルの多言語化やOJT計画の策定を行い、技術移転と運用定着をスムーズに進めます。
サステナブル施策とタイEV補助金の接点

EV普及が進むタイでは、大気汚染対策や再生可能エネルギー導入といったサステナブル施策と、タイEV補助金の優遇措置が密接に連携しています。以下3つの視点で、その接点を見ていきましょう
PM2.5対策とEV推進の関連性を理解する
都市部の大気汚染(PM2.5)は、主に化石燃料車の排ガスが原因です。EVへの転換は、大気中の微小粒子を削減し住民の健康を守る効果があります。
森林管理やコミュニティ林の保全プロジェクトに対し、PM2.5削減を目的とした投資奨励が適用されます。電動車両導入と並行して地域レベルでの植樹や防火帯整備を実施することで、補助金の環境負荷軽減要件を満たせます。
太陽光発電や省エネ設備との組み合わせを活用する
EV製造工場の電力を再生可能エネルギーで賄うことで、温室効果ガス排出削減効果を高められます。
太陽光発電設備(PVモジュール・インバータ等)や省エネ機器への投資に対し、機械輸入関税免除・3年の法人税免除が適用されます。1MWあたり40MTHB以内の投資で最大優遇を得られる設定です。
地域支援制度や教育支援と組み合わせる
公教育機関向けの研修施設整備や、公立医療機関への環境機器寄贈も、PM2.5削減プロジェクトとして支援対象になります。
EV技術者育成のための実践研修やワークショップ費用が補助金対象に含まれ、サステナビリティ人材の底上げと現地定着を同時に実現します。
タイEV補助金の申請手順と活用ステップ

補助金申請は、段取りを失敗すると計画が頓挫しかねません。タイEV補助金をスムーズに受給するための3つのステップを解説します。
事前相談〜奨励申請までの流れを確認する
まずはBOI窓口や補助金公募事務局への事前相談からスタート。事前相談では、事業計画の概要や導入予定機器のスペックを提示し、補助対象要件の適合性を確認します。その後、正式申請書類を提出し、書類審査→現地ヒアリング→奨励証交付という流れです。事前相談から交付まで約8〜12週間を見込み、スケジュールに余裕を持つことが重要です。
設備導入・報告・評価フェーズを実行する
奨励証取得後は、実際に機器を導入し、稼働状況を記録します。導入後30日以内に「導入完了報告書」を提出し、補助対象機器が要件通りに稼働しているかを示すデータ(稼働ログ、省エネ実績など)を添付しましょう。次に、補助金交付前の評価フェーズとして現地調査や性能試験を受け、最終的な交付決定を得ます。
必要書類や工程表を整備する
成功の鍵は書類管理と進捗可視化です。
- 必要書類:事業計画書、設備仕様書、見積書、稼働ログ、写真記録など。
- 工程表:事前相談〜導入〜報告までの各フェーズを週単位で細分化し、担当者や期日を明示する
社内外の関係者が同じ進捗を共有できれば、書類不備や手戻りを未然に防ぎ、タイEV補助金を受給できます。
タイEV補助金を活用する際の注意点

EV補助金とBOI優遇を賢く組み合わせるには、制度の細かい要件把握と自社計画の整合性が不可欠です。申請前後に陥りがちな3つの落とし穴を整理します。
税免除対象や設備要件の誤認を防ぐ
補助金公募要領には、法人税・輸入関税免除の対象設備・期間が細かく記載されています。たとえば、EVバッテリー製造ラインでは「セル組立装置のみ」ではなく「セル検査装置まで含める」と明記されることがあります。要件書と自社の設備計画を詳細に突き合わせ、免除対象外となる機器を事前に洗い出すことで、交付決定後の追加負担を回避できます。
BOI区分と実行内容のミスマッチを回避する
BOI制度には複数の奨励区分(Import Duty, Corporate Tax, Land Ownershipなど)があり、申請時の区分選択が適用範囲を左右します。たとえば「輸出用部品免除」を選んだ場合、国内販売向け生産は対象外になるケースも。自社の生産・販売スキームに最適な区分を選び、計画書に実績想定を明記することで、制度とのミスマッチを防ぎましょう。
恩典取消リスクを制度理解で抑制する
一度交付決定を受けた後でも、要件逸脱や報告漏れがあると優遇措置が取り消され、過去に遡って課税されるリスクがあります。特に、稼働率や省エネ実績の報告は定量データが求められるため、導入前にモニタリング体制を整備し、定期的にログと証憑を保管しておくことが重要です。これにより、交付後の監査でも安心して対応できます。
TOMASTECHが支援できる領域と特徴

TOMASTECHは、制度適用から技術設計、現場運用までを一気通貫でサポートします。以下3つの視点で当社の強みをご紹介します。
管理システムと補助対象設備の構成を設計する
EV生産ラインでは、バッテリー製造からリサイクルまでを一貫して管理できるシステムが必要です。TOMASTECHは、MESやエネルギー管理ツール、バッテリー履歴管理システムを組み合わせた最適構成を設計。補助金の対象要件を満たす性能基準をクリアしつつ、現場運用の手間を最小化する設計図を提供します。
制度対応に必要な仕様設計をサポートする
補助金やBOI制度の申請には、技術仕様書やRFPで性能要件を明確に示すことが必須です。TOMASTECHでは、公募要領に沿った「省エネ率」「検査精度」「稼働率」などの指標を仕様書に落とし込み、発注先や審査機関にも一目で分かるドキュメントを作成。事前相談時の技術説明でも、審査官からの照会を最小限に抑えられるよう支援します。
導入〜人材育成〜現地運用まで一気通貫で伴走する
機器据付や稼働試験が終わってからが本番です。TOMASTECHは、現地スタッフ向けの多言語マニュアル作成、OJTプログラム設計、運用トラブルシューティングまで現場レベルで伴走。さらに、交付後のフォローアップ報告書作成や定期的な運用状況レビューも実施し、補助金交付後も安心してご利用いただける体制を整えます。
タイのEV補助金に関するよくある質問

ここからは、タイのEV補助金に関するよくある質問に回答していきます。
EV補助金の申請対象となる具体的な設備例は?
EVバッテリー製造では、自動化ロボット(組立・セル搬送)、精密加工機械(公差管理用)、およびエネルギー管理システム(EMS)が主に対象です。さらに、製造実行システム(MES)やAI検査装置も補助対象となります。
補助率や上限額はどのくらい?自社規模別の目安は?
ものづくり補助金では、設備投資額の1/2を上限に最大4,000万円まで支援されます。中小企業省力化投資補助金は上限1億円、IT導入補助金は最大450万円が目安です。自社年商や従業員規模が大きいほど、グローバル枠等を活用して高額支援を狙えます。
地域ごとの公募要件や優遇条件の違いはある?
基本的に補助金の性能要件は全国共通ですが、イースタンシーボード(東海岸経済回廊)や工業団地内では、地元振興枠として追加支援率や優遇期間が延長される場合があります。また、北東部などの特別経済区では人件費補助など独自枠が設けられています。
まとめ|タイEV補助金を成果につなげるために

タイEV補助金を最大限に活用し、投資効果を確実な成果に結びつけるためのポイントを整理します。
- 制度に通る構成設計を徹底する
- 技術と制度を両面から捉える視点を持つ
- 信頼できる実行パートナーと連携する
これらを組み合わせることで、タイEV補助金を単なる資金調達手段にとどめず、真の競争力強化と持続可能な成長につなげることが可能です。ぜひ、計画段階から制度・技術・実行の全体最適を意識して取り組みましょう。
現地法人設立からシステム設計、現場実装、トレーニングまで一気通貫で伴走できるパートナー選びが鍵です。
TOMASTECHは多言語対応のドキュメント作成からOJT設計、フォローアップ報告書まで幅広く支援します。
タイEV補助金を最大限に活用したい方は、お気軽にお問い合わせください。