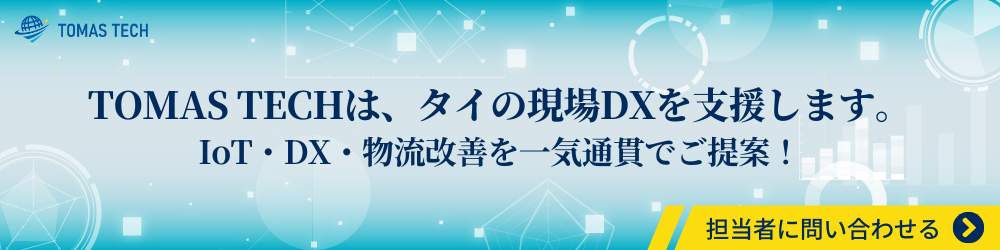東南アジアの産業は、製造業が輸出を支えつつ、デジタル経済やEV・再エネの拡大が進んでいます。ASEANは人口約6.8億の成長圏です。タイ・ベトナム・インドネシアは産業基盤と政策が異なり、調達と販売の設計で最適解が変わるので注意が必要です。
本記事では、市場規模・産業構造・政策の3軸で主要国を比較し、分散と近接生産の視点から進出判断の勘所を紹介します。
東南アジア産業の全体像と主要国との比較

ASEANは総人口6億人を超える巨大市場であり、世界的にも存在感を増しています。域内の製造業は輸出を支える基幹産業であり、自動車・電子機器・繊維を中心に国ごとに強みを形成してきました。近年はデジタル経済や再生可能エネルギー、EV分野といった新しい成長分野も急伸しています。
参照元:ASEANStatsDataPortal: Indicators
日本企業にとっては、単なる製造拠点ではなく、成長市場としての販売機会や技術協力の余地が広がっており、進出判断の材料となります。
ここからは、東南アジア産業の全体像と主要国との比較をみていきましょう。
タイ・ベトナム・インドネシアの産業構造
東南アジアの中でも、タイ・ベトナム・インドネシアは日本企業の進出先として特に注目されています。
それぞれの産業構造には明確な違いがあり、国別の強みを把握することが戦略立案の第一歩です。
以下は、ASEAN Key Figures / Statistical Yearbook の公開データを基に整理した概観です。
| 国名 | 主力産業 | 製造業比率(GDP) | 主な輸出品目 | 政策の方向性 |
| タイ | 自動車・電子機器・化学 | 約25%前後 | 自動車・電子部品・化学品 | 「タイ4.0」で次世代産業(EV、バイオ、デジタル等)を重点育成 |
| ベトナム | 電子機器・繊維・農産加工 | 約24%前後 | 電子機器・衣料品・農産品 | 「デジタル経済戦略」で半導体・ICT分野の強化 |
| インドネシア | 鉱業・エネルギー・食品加工 | 約20%前後 | 石炭・パーム油・鉱物資源 | 「Making Indonesia 4.0」で製造業高度化とEV電池産業育成 |
参照元:「ASEAN KEY FIGURES 2021 – ASEANstats」
各国の特徴は以下の通りです。
- タイ:日系自動車メーカーや電子機器メーカーの拠点が集積。ASEANの「工場」として確固たる地位を築く。
- ベトナム:低コスト労働力とFTAを活かし、繊維や電子分野で輸出を急拡大。近年はICTやデジタル産業の成長にも注目が集まる。
- インドネシア:豊富な天然資源を背景に鉱業・エネルギー分野が強い。EV電池のサプライチェーンを構築する動きが加速。
このように、各国は産業基盤や政策の方向性が異なり、日本企業が進出する際は自社の強みと照らし合わせて選定することが重要です。
サプライチェーン再編と日系投資の動向
パンデミックや米中摩擦を契機に、グローバルサプライチェーンは「一極集中」から「分散と近接化」へと移行しています。その受け皿としてASEANの存在感は一段と高まりました。2023年のASEAN域内外国直接投資(FDI)は2,240億ドルと前年を上回り、そのうち製造業とデジタル分野で全体の4割を占めています。
参照元:ASEAN Investment Report 2024(ASEAN/UNCTAD)
日本企業の投資動向をみると、自動車・電子機器・化学分野での進出が際立ちます。背景には、調達リスクの分散と、成長市場でのシェア拡大という二つの狙いがあります。
- タイ:EVや電子機器の集積を軸に、完成車・部品輸出の拠点化を強化。
- ベトナム:半導体やスマートフォンを中心とした電子機器の新拠点として外資投資が急増。
- インドネシア:ニッケル資源を背景に電池・電動車分野への大型投資が集中。食品加工や自動車市場も拡大。
参照元:Thailand Board of Investment(BOI)
参照元:Vietnam Government Decision No.411/QD-TTg
これらの動きは、ASEANが単なる「生産の場」から、資源・市場・人材を包含した「戦略的拠点」へと進化していることを示しています。日本企業にとっては、ASEAN内の国ごとに強みを掛け合わせ、調達リスクを抑えながら需要を取り込む戦略が求められる段階に入っています。
【国別】産業政策の骨子
東南アジア主要国は、産業政策を通じて自国の成長分野を明確に位置づけています。産業構造の違いに加え、政府の方向性を理解することが進出先選定の大きな判断材料となります。
【タイ「Thailand 4.0」】
Sカーブ産業(次世代自動車、スマートエレクトロニクス、医療、バイオテクノロジー、デジタル産業など)を重点育成。特に東部経済回廊(EEC)では、日系製造業やEV関連の集積を推進。
【インドネシア「Making Indonesia 4.0」】
優先5業種(食品・繊維・自動車・電子機器・化学)を対象に、デジタル導入と生産性向上を図る戦略。鉱物資源を活用したEV電池産業育成も加速。
【ベトナム「国家デジタル経済・社会発展戦略」】
2030年までにGDPの30%をデジタル経済が占めることを目標に設定。電子商取引やICT産業に加え、データセンターや半導体分野で外資誘致を強化。
比較表にまとめると以下の通りです。
| 国名 | 政策名 | 重点分野・特徴 |
| タイ | Thailand 4.0 | Sカーブ産業(自動車・エレクトロニクス・医療・デジタル) |
| インドネシア | Making Indonesia 4.0 | 優先5業種(食品・繊維・自動車・電子・化学)、EV電池育成 |
| ベトナム | デジタル経済・社会戦略 | デジタル経済比率30%目標、半導体・データセンター誘致 |
これらの政策は、単なる製造業の強化にとどまらず、デジタル・エネルギー・次世代技術を組み込んだ「産業高度化」を意識しています。外資にとっては、政策の重点分野と投資先を重ねることで、税制優遇やインフラ整備の恩恵を受けやすい点が重要です。
参照元:Ministry of Industry Republic of Indonesia – Making Indonesia 4.0
参照元:Decision No.411/QD-TTg – National Strategy on Digital Economy and Society Development
東南アジア産業で伸びやすい分野

製造業を中心に発展してきた東南アジアですが、今後は従来の強みに加え、デジタル・EV・再エネといった新分野がさらに成長すると予測されています。ASEAN各国は政策的にもこれらの分野を重点に据えており、外資企業にとっては進出・拡大の好機が広がっています。
製造業の産業集積(電子機器・自動車部品・繊維)
ASEAN域内の製造業は、国ごとに強みを持ち、部材・加工・組立までを分担する「地理的な役割分担」が形成されています。
- 電子機器:ベトナムがスマートフォンや半導体組立の拠点に急成長。タイやマレーシアも電子部品の製造・輸出で存在感。
- 自動車部品:タイは「アジアのデトロイト」と呼ばれるほど自動車関連産業が集積。インドネシアも国内市場の強さを背景に自動車部品の需要拡大。
- 繊維産業:ベトナムやカンボジアが欧米向け衣料品輸出の拠点として発展。低コスト労働力とFTAを活用。
比較すると、次のように整理できます。
| 分野 | 主な集積国 | 特徴 |
| 電子機器 | ベトナム、タイ、マレーシア | 半導体・スマホ組立、電子部品製造で急成長 |
| 自動車部品 | タイ、インドネシア | 完成車と部品の集積、域内需要も拡大 |
| 繊維 | ベトナム、カンボジア | 欧米市場向け輸出拠点、低コストとFTAを武器に成長 |
このような産業集積は、単独の国だけでなくASEAN全体で補完関係を築いている点が特徴です。電子機器や自動車部品のように川上から川下まで一貫した供給網がある分野は、今後も競争力を維持しやすいと考えられます。
デジタル経済とデータセンター・半導体
東南アジアのデジタル経済は2024年の取引総額(GMV)が2,630億ドル、前年比+15%で拡大しました。eコマースやオンラインメディアに加え、AI導入が次の成長要因として整理されています。
クラウド各社の投資が加速しています。AWSは2025年1月にタイ(バンコク)リージョンを商用提供し、2037年までに総額約50億米ドルの投資計画を公表しました。マイクロソフトはインドネシアで今後4年間に17億米ドルを投じ、AI・クラウド基盤と人材育成を進めると発表しています。
データセンターはマレーシア(とくにジョホール)で急伸しています。一方で電力料金改定や電力確保が課題として報じられ、事業者は再エネ調達や省エネの取り組みを模索しています。
半導体では、マレーシアが世界の後工程(組立・封止・テスト)シェア約13%を担い、上位企業の追加投資が継続しています。タイはPCBサプライチェーンまで優遇対象を拡大。ベトナムは2030年までに半導体エンジニア5万人育成の計画を進めています。
| 国・地域 | データセンター / クラウド | 半導体・人材 | 補足ポイント |
| タイ | AWSが2025年1月に商用リージョン稼働 | PCBサプライチェーンまでBOI優遇を拡大 | DC・製造集積の相乗効果を狙う動きが可視化。 |
| ベトナム | 大規模クラウド投資の誘致が継続 | 2030年までに半導体エンジニア5万人育成 | 電子・半導体OSAT/設計人材の底上げを政策化。 |
| インドネシア | MSがAI・クラウドに17億ドル投資 | 電池・電子の製造集積を活用 | 首都圏を中心にDC需要が拡大傾向。 |
| マレーシア | DC需要が急拡大、電力コストが論点 | 後工程シェア約13%、上位企業が増設 | エネルギー確保と高度化の両立が焦点。 |
「AI×クラウド×再エネ」の組み合わせが、DC立地と運用の成否を左右します。後工程に強いマレーシア、電子組立に強いベトナム、産業基盤の厚いタイ——強みの異なる国を組み合わせた分業が現実的です。人材面では、設計・テスト・品質保証を担う現地エンジニアの育成スキームを早期に用意すると、量産や監査対応の立ち上がりが早まります。
EV・再エネの政策と設備投資
東南アジアでは、自動車産業の電動化と再生可能エネルギーの導入が同時に進んでいます。背景には、各国が掲げる脱炭素目標や、域内の電力需給の逼迫リスクがあります。ASEAN全体としては「一次エネルギーに占める再エネ比率を2025年までに23%」「発電設備容量に占める再エネ比率を35%」といった目標を設定していますが、2022年時点では一次エネルギー比率が約15.6%にとどまり、目標達成には追加投資が不可欠です。
EV分野では、各国が自国の強みを活かした政策を打ち出しています。タイは「EV3.5」スキームを開始し、輸入台数に応じた現地生産を求める条件を導入しました。これは、単なる補助金支給ではなく、生産拠点を確実に誘致する仕組みです。インドネシアは豊富なニッケル資源を背景に、電池分野への外資投資を積極的に呼び込み、税優遇を拡充。ベトナムも物品税の大幅引き下げや登録手数料免除を通じて市場需要を後押ししています。
理解を助けるために、主要国の政策を整理すると次の通りです。
| 国名 | 政策の特徴 | 補足 |
| タイ | EV3.5スキーム(輸入と生産をリンク)、2030年までに国内生産の30%をEV化 | 東部経済回廊を中心に完成車メーカーの集積 |
| インドネシア | 物品税免除・輸入税猶予・VAT減免など税制優遇、ニッケル下流化政策で電池投資拡大 | EV電池サプライチェーンの拠点化を加速 |
| ベトナム | EVの物品税を3%に引下げ、登録手数料免除を2027年まで延長 | 販売需要の刺激を重視 |
再生可能エネルギーでも同様に投資機会が広がっています。IEAの見通しでは、2035年までに電力需要増の35%以上をクリーンエネルギーが担うとされ、太陽光や風力が主役になると予測されています。ASEAN全体の発電設備容量は2022年の315GWから、2050年には1,100GWを超える水準まで拡大する見込みです。
つまり、東南アジアのEV・再エネ市場は「政策の後押し」「資源を活かした戦略」「電力需給の現実」という3つの要素が重なり合って成長しています。日本企業にとっては、自動車分野での既存ネットワークを軸にしつつ、再エネや電池など新領域に踏み込むことで、中長期的な事業機会を確保できるでしょう。
東南アジア産業における日本企業の進出ポイント

ASEAN市場は人口規模の拡大、製造集積、デジタル経済の急成長を背景に、多様な投資機会を提供しています。しかし同時に、国ごとに政策やインフラ環境が異なるため、日本企業が成果を上げるには「自社の強み」と「現地の特性」を重ね合わせた進出戦略が欠かせません。とくに注目すべきは、調達・品質・人材という3つの観点です。
近接生産と分散調達で納期短縮を武器に受注を伸ばす
世界的にサプライチェーンの再編が進む中、東南アジアは「中国一極集中からの分散先」として脚光を浴びています。日本企業にとっては、タイ・ベトナム・インドネシアといった国々に生産・調達拠点を分散することで、納期リスクを軽減しやすくなります。
- タイでは自動車・電子部品の一貫生産が可能で、完成車や家電の即応性を確保できる
- ベトナムでは電子機器の組立や半導体後工程が強く、短納期の大量生産に適する
- インドネシアでは資源を基盤とした電池・部材調達が拡大し、部品供給網の選択肢が広がる
こうした「近接生産+分散調達」を組み合わせることで、顧客からの短納期要求やリスク分散ニーズに応えやすくなります。
品質・安全・トレーサビリティ対応で監査要求に先回りして選ばれる
日本企業が東南アジアで信頼を得るうえで欠かせないのが、品質保証とトレーサビリティ体制の構築です。グローバルサプライチェーンでは、製品の安全性や環境対応を証明するデータを即時に提示できるかどうかが取引条件となりつつあります。とくに自動車や電子機器、食品などの分野では、監査や国際規格への準拠が強く求められています。
多くの企業が直面する課題は以下のとおりです。
- 品質基準の高度化:欧米顧客を中心にISOやIATFなどの国際認証取得が必須に
- トレーサビリティ要求:部品や素材の生産履歴をデジタルで管理・提出する仕組みが必須に
- サステナビリティ対応:CO2排出や再エネ利用の証明を監査で求められるケースが増加
こうした要求に対して、早い段階からデジタル化された品質・工程管理システムを導入すれば、現地拠点でも国際基準を満たす運営が可能となります。先回りして対応することで、競合との差別化につながり、調達先候補として優先的に選ばれる可能性が高まります。
参照元:ASEAN Investment Report 2024(ASEAN/UNCTAD)
現地パートナー連携と人材育成で量産立ち上げを短縮する
東南アジアに進出した日本企業が直面する大きな課題の一つが「量産立ち上げのスピード」です。需要が拡大する市場に応えるには、製造設備を整えるだけでなく、現地の人材育成やパートナーとの信頼関係をいかに早期に築けるかが鍵となります。
とくにASEANでは、制度やインフラ整備が国ごとに異なるため、自社単独での対応には限界があります。そのため、多くの企業が以下の取り組みを組み合わせています。
- 現地パートナーとの合弁・提携:土地・規制・労務管理に強いパートナーと組むことで、操業リスクを軽減。
- 人材育成プログラムの導入:製造業では技能工からエンジニアまで幅広い層の育成が必要。各国政府も職業訓練やSTEM教育を強化中。
- 短期研修+長期派遣のハイブリッド:日本本社での短期集中研修と、現地でのOJTを組み合わせることで、習熟までの期間を短縮。
こうした取り組みは、単に「人材確保」にとどまらず、品質・納期・安全の基準を早期に浸透させる効果があります。その結果、監査や顧客要求に対応できる体制を短期間で整備でき、競争優位につながります。
参照元:
- ASEAN Key Figures 2023(ASEANstats:労働市場・教育統計)
- ASEAN Investment Report 2024(UNCTAD/ASEAN:FDI動向と人材需要分析)
- Vietnam National Digital Transformation Program(ベトナム政府:人材育成戦略)
東南アジア産業におけるインフラ・人材・制度の課題とポテンシャル

東南アジアは成長市場として投資の注目を集めていますが、同時にインフラや人材、制度面での制約が存在します。電力や物流の不足、教育水準の地域差、税制や環境規制の不透明さなどは、事業拡大を阻む要因となり得ます。ただし、各国はこれらの弱点を改善する政策を打ち出しており、将来に向けたポテンシャルも大きい分野です。
電力・港湾・物流のボトルネック
製造業やデジタル経済の拡大に伴い、エネルギーと物流の制約が浮き彫りになっています。とくに電力インフラは、再エネ導入と同時に安定供給の確保が課題です。IEAの見通しでは、ASEANの電力需要は2035年までに現在の1.5倍以上へ拡大すると予測されており、電源投資の遅れがリスク要因となっています。
港湾・物流面でも、ハブ港湾の能力不足や道路・鉄道インフラの遅れがサプライチェーンのボトルネックです。タイやベトナムでは港湾拡張が進められていますが、旺盛な輸出需要を支えるには十分とは言えません。
課題を整理すると以下の通りです。
- 電力:再エネ拡大と送配電網の近代化が追いつかず、供給安定性に懸念
- 港湾:主要港湾の混雑が慢性化、輸送リードタイムが長期化
- 物流:内陸部の道路・鉄道不足により、製造拠点から港までの輸送効率が低い
こうした制約は投資リスクである一方、政府が重点的に改善を進める分野でもあります。インフラ開発プロジェクトへの外資参加や官民連携は、企業にとって長期的な機会となる可能性があります。
人材需給と教育投資の計画
東南アジアの持続的な成長を支えるためには、人材の量と質の両立が欠かせません。製造業の集積に加え、デジタル経済や再エネ分野の拡大により、エンジニアやITスキルを持つ人材への需要は年々高まっています。一方で、労働市場の構造は国ごとに異なり、人材需給のギャップが課題となっています。
- タイ:自動車・電子分野で技能工は豊富だが、AIやデジタル領域の高度人材が不足。BOIは「人材開発基金」を通じてSTEM教育を強化。
- ベトナム:若年人口が多く、労働力供給に余裕がある一方、半導体・ICT分野で専門人材の不足が目立つ。政府は「2030年までに半導体エンジニア5万人育成」を目標に掲げる。
- インドネシア:人口規模を背景に労働力は豊富だが、教育水準の地域差が大きい。職業訓練(TVET)の拡充を国家戦略に組み込み、製造・物流分野の人材育成に投資。
これらの取り組みは単なる教育支援にとどまらず、外資誘致の条件整備にも直結しています。企業が進出する際、即戦力となる人材の確保や、長期的に育成できる環境が整っているかは大きな判断材料です。
制度・税制・環境規制
東南アジアで事業を展開する際には、各国の制度や税制、そして環境規制の違いを正しく把握することが重要です。インフラや人材の課題に比べて見えにくい分野ですが、コストや事業の持続性に直結するため、進出企業にとって大きなリスク要因にもなります。
進出判断を行う際には、以下の観点をチェックリストとして整理しておくことが実務的です。
- 外資規制の有無(業種別の参入可否)
- 投資奨励制度の対象分野と優遇条件
- 現地法人設立に必要な手続きの複雑さ
- 法人税率と軽減措置の有無(ベトナムは最長15年の優遇)
- 研究開発投資や人材育成への税控除制度(インドネシアの「スーパーダクション」)
- 輸出加工区・特区の税制インセンティブ
- 工場建設に必要な環境影響評価(EIA)の有無と提出条件
- 再エネ利用や廃棄物処理計画の提出義務(マレーシア)
- 炭素排出モニタリングや報告義務の範囲(ベトナム環境保護法)
多くの国で外資規制は段階的に緩和されていますが、特定分野では依然として制約が残っています。タイではBOIの投資奨励制度により、製造・R&D拠点に税制優遇が適用される一方、物流やサービス分野は外資規制が厳格に残されています。
ベトナムでは、ハイテク分野や輸出加工区に進出する企業に対し、法人税の優遇措置(最長15年の軽減)が設けられています。インドネシアも「スーパーダクション」と呼ばれる税控除制度を導入し、研究開発投資に対して最大200%の控除を認めています。
各国は再エネ導入を加速する一方で、環境規制も強化傾向にあります。マレーシアでは2023年に環境影響評価(EIA)の要件が厳格化され、一定規模以上の工場建設には再エネ利用や廃棄物削減計画の提出が必須になりました。ベトナムも新たな環境保護法により、炭素排出のモニタリング義務を強化しています。
東南アジア産業のDX・トレーサビリティ・生産管理はTomastechにご相談ください

MES・トレーサビリティ・生産管理システムで現場改善
製造現場では、「どのラインで・いつ・誰が・どの資材を使ったのか」 を正確に記録し、必要なときに即時に提示できる体制が求められます。これは海外顧客や監査機関からの信頼を得るうえで欠かせません。
Tomastechは以下のようなソリューションを提供しています。
- MES(製造実行システム):作業・進捗・品質のリアルタイム管理
- トレーサビリティ管理:原材料から出荷までの履歴を一元的に記録
- 生産管理システム:計画・投入・実績を統合し、効率的なライン運用を実現
これにより、製造リードタイム短縮や不良率低減だけでなく、監査や規制対応にも強い現場体制を構築できます。
進出後のDX運用を並走
システム導入はゴールではなく、定着化までが重要です。Tomastechは、導入初期のPoC(概念実証)から本番展開、さらに運用定着まで一貫して支援します。
- 初期フェーズ:現場課題を洗い出し、小規模PoCで効果を検証
- 拡張フェーズ:本番展開にあわせ、複数ラインや拠点へ横展開
- 定着フェーズ:現場教育やデータ活用をサポートし、改善活動を持続可能に
単なるシステム導入ではなく、「成果を現場で根付かせる伴走型サポート」がTomastechの強みです。
東南アジア進出を検討中、あるいはすでに拠点を構えている企業の皆さまへ。
「品質管理を現地で徹底できるか不安」「DXを導入しても定着しない」 そんな課題を抱えていませんか?
Tomastechは、製造業に特化したDX・トレーサビリティ・生産管理の専門チームとして、御社の現場改善を伴走支援します。
アジアでの競争力を高めたい企業様は、ぜひ一度ご相談ください。